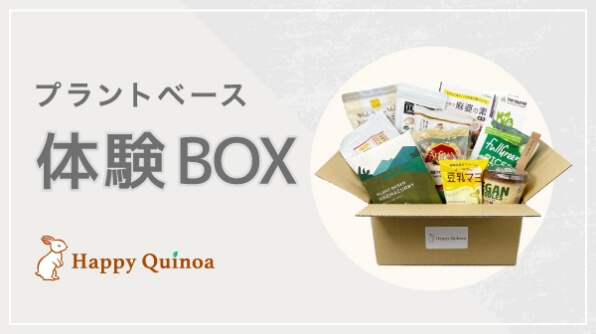無印良品から大豆ミートリリース!ヴィーガン?成分情報は?など徹底解説

無印良品から大豆ミートがリリース!成分情報を調査し、ヴィーガン対応であるかについても徹底解説します。その他、無印良品のエシカルな取り組みについても紹介します。

無印良品の大豆ミートはヴィーガンなのか?
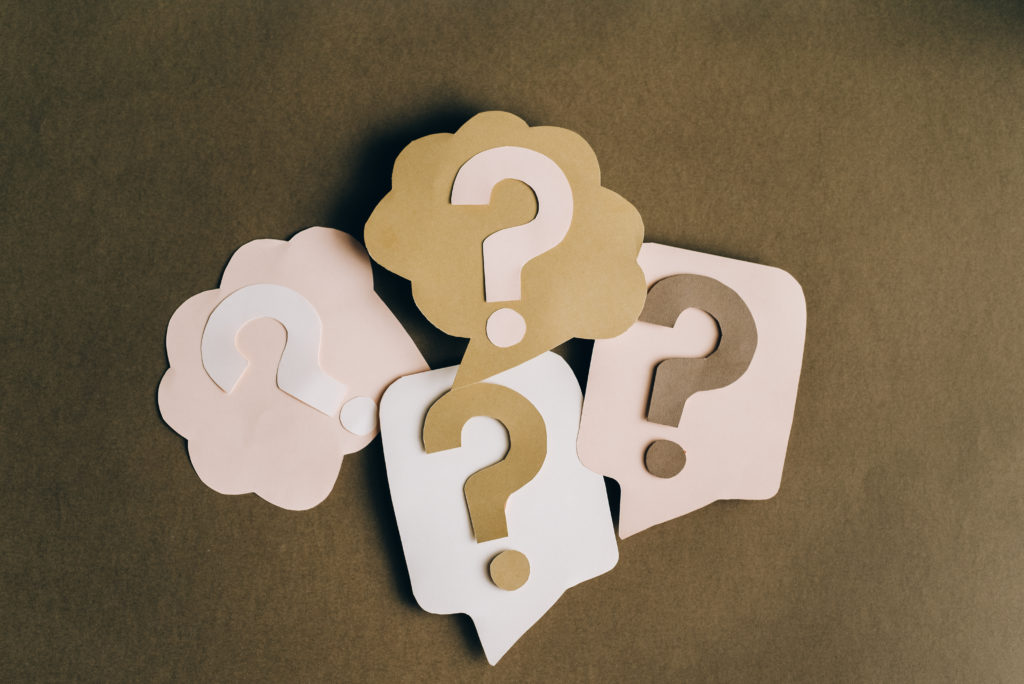
ここで、「無印良品の大豆ミートはヴィーガンなのか?」について、商品表示情報・原材料を調べて分かったことをまとめます。
ヴィーガンなのか否かは、原材料と製造過程を考える必要があるため、その点をご説明します。
結局のところヴィーガンなの?
VEGAN認証のない製品の場合、原材料のみでヴィーガンと考えるか、または、製造過程も含めて考えるかは、個人の判断に委ねられると言えます。
上記を踏まえ、以下に、「原材料」・「製造過程」に分けて、「無印良品の大豆ミートはヴィーガンなのか」まとめましたので、参考にしてください。
【原材料のみでヴィーガン・ベジタリアン向けなのか判断した場合】
- 「ハンバーグ」と「ミートボール」は、原材料の一部に卵や乳成分が含まれており、ヴィーガン向けではないが、ベジタリアン向けではある。
- 「ひき肉タイプ」と「薄切りタイプ」は、原材料に卵や乳成分が含まれていないため、ヴィーガン・ベジタリアン向けである。
【製造過程も含めてヴィーガン・ベジタリアン向けなのか判断した場合】
- 「ハンバーグ」と「ミートボール」(上記で既にヴィーガン向けではないと判明)
→エビ・カニなどを含む製品と共通の設備で製造されているため、個人の判断によっては、ベジタリアン向きではない。 - 「ひき肉タイプ」と「薄切りタイプ」
→エビ・カニ・卵・乳成分などを含む製品と共通の設備で製造されているため、個人の判断によってはヴィーガン・ベジタリアン向けではない。
今回ご紹介した「無印良品の大豆ミート」は、VEGAN認証を取得はしていないようですので、その点を重視される方には、不向きな製品と考えられます。
しかし、その判断は個人に委ねるのが現実的かもしれません。
今後、原材料、製造過程も含めて、100%植物性食品だけのヴィーガンに対応した製品が登場することを期待したいですね!
VEGAN認証の基準
日本でVEGAN認証を与えている、ベジプロジェクトジャパンのVEGAN認証の基準は以下の通りです。
・ヴィーガン:原材料として、肉魚介類卵乳製品はちみつ等、動物に由来する物を含まないことが確認できたものを、ヴィーガンと定義致します。
揚げ油に関しては植物油であっても動物性の食品を同じ油で揚げていないこととします。
アルコール飲料に関しては、精製・加工過程に動物由来の物質が清澄材として用いられていないこと、原材料に記載される砂糖に関しては濾過・脱色工程に骨炭が使用されていないこと、および商品自体の開発時に動物実験が行われていないことも確認させて頂きます。
製造過程における同じ設備・食器で動物性のものの使用がありコンタミネーションが起こり得る場合は、認証取得商品製造前のラインの洗浄とメニューまたは商品にその旨を明記することを義務付けております。
多数存在するベジタリアン・ヴィーガンの定義と弊法人認定の当マークにより認証される定義が必ずしも一致するものではありません。
・ベジタリアン:原材料として、肉魚介類昆虫等、それらに由来する物を含まないことが確認できたものをベジタリアンと定義致します。
揚げ油に関しては植物油であっても肉魚介類昆虫等を同じ油で揚げていないこととします。
アルコール飲料に関しては、精製・加工過程に動物由来の物質が清澄材として用いられていないこと、原材料に記載される砂糖に関しては濾過・脱色工程に骨炭が使用されていないこと、および商品自体の開発時に動物実験が行われていないことも確認させて頂きます。
製造過程における同じ設備・食器で肉魚介類昆虫等の使用がありコンタミネーションが起こり得る場合は、商品にその旨を明記することと認証取得商品製造前のラインの洗浄を義務付けております。
多数存在するベジタリアンという定義と弊法人認定の当マークにより認証される定義が必ずしも一致するものではありません。
(引用元:ベジプロジェクトジャパン「弊法人が定める、ベジタリアンおよびヴィーガンの基準とその他」)
View this post on Instagram
上記の基準には、「製造過程における同じ設備・食器で動物性のものの使用がありコンタミネーションが起こり得る場合は、認証取得商品製造前のラインの洗浄とメニューまたは商品にその旨を明記することを義務付けております」とあります。
「コンタミネーション」とは、製造・調理工程において原材料には使用していない物質が意図せず混入すること、もしくは、混入する可能性があることを指します。
そのため、調理器具などの洗浄がなされずに作られる場合、ヴィーガンではないという考え方も可能となります。
しかし、VEGAN認証機関の認証基準に従うことで、加工食品の購入や外食に際し、選択肢が狭まるのも事実です。