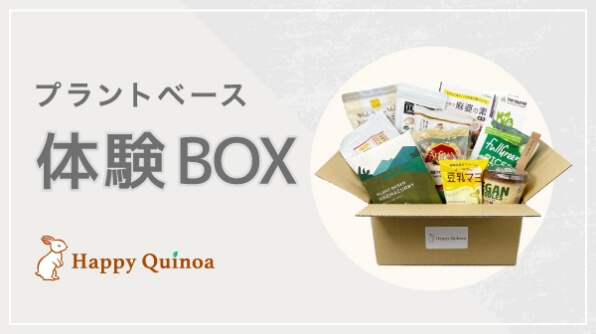台湾式の菜食文化、台湾素食とは? ヴィーガンとの違いも解説

日本からの旅行先としても人気の台湾では、「台湾素食」という菜食文化があり、国民の約14%が素食を選択しているといわれております。台湾素食の定義やヴィーガンとの違い、素食が文化として根付いている背景等を徹底解説します。台湾を訪れる際はぜひ、台湾素食を堪能ください。

ヴィーガンへの興味の延長線上で、その存在を知られた方もいれば、台湾旅行などを通して、台湾を入口にお知りになられた方もいらっしゃるかと思います。
今回は、「台湾素食」について、ヴィーガンとの違いにも触れながら、台湾素食の定義や台湾で素食文化が広まっている理由などを、詳しくご紹介いたします。
台湾素食とは?
View this post on Instagram
元々、中国語の「素食」という言葉は、「菜食」のことを意味します。
素食という菜食文化は、台湾だけでなく、中国や香港でも浸透している文化なのですが、実はそれぞれ微妙に定義が異なります。
今回は、その中でも「台湾素食」の定義についてご紹介します。
台湾素食については、飲食する範囲に応じて5つに分類され、それぞれ以下のように台湾政府によって定義されています。
(1) 全素・純素(チュエンスー):純粋な植物性食品のみを摂取します。5種類の植物性香辛料(ネギ、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、タマネギ)は摂取しません。
(2) 蛋素(ダンスー):全素・純素の範囲に加えて、卵製品を摂取します。
(3) 奶素(ナイス―):全素・純素の範囲に加えて、乳製品を摂取します。
(4) 奶蛋素(ナイダンス―):全素・純素の範囲に加えて、卵製品・乳製品を摂取します。
(5) 植物五辛素(ジーウーウーシンスー):純粋な植物性食品を摂取しますが、5種類の植物性香辛料や乳・卵を含むこともあります。
(出典:行政院衛生署公告「包裝食品宣稱為素食之標示規定」)
以上の素食の定義は、政府が定めた食品衛生法で定義されており、台湾で「素食」をうたった製品を販売する場合は、その製品がどの素食グループに該当するかの製品表示もしなければならないようです。
素食について、政府がルールを定めている所からも、台湾という国に素食文化が根強く浸透していることがうかがえますね。
ヴィーガンやベジタリアンとの関係性は?
View this post on Instagram
次に、台湾素食とヴィーガンやベジタリアンとの関係性について、ご紹介します。
ヴィーガンとは、動物性の食品を一切摂取しない、「完全菜食主義」のことです。
この、「ヴィーガン」という用語は、1944年にイギリスのヴィーガン協会(The Vegan Society)が創設された際に命名されました。参考までに、「ヴィーガン」とは、「ベジタリアン」から派生した造語であり、「Vegetarian」の「Veg」と「an」取って、「Vegan」となったようです。
また、ベジタリアンとは、野菜や穀物を中心とし、肉や魚、肉・魚の加工品も食べない「菜食主義」のことを言います。
ヴィーガン・ベジタリアンの定義について、詳しくは、「ヴィーガンになる理由とは?定義やベジタリアンとの違い」を参考にしてください。
以上を踏まえて、台湾素食と、ヴィーガン・ベジタリアンそれぞれの定義を比較すると、台湾の素食分類である全素・純素=ヴィーガンであり、蛋素・奶素・奶蛋素・植物五辛素=ベジタリアンといえます。
*ヴィーガンもベジタリアンも、更に様々な種類に分けられますが、今回は、広義のヴィーガン・ベジタリアンと、台湾素食の関係性を紹介させていただきました。
台湾素食の人口は?
View this post on Instagram
台湾の素食人口は約330万人いるといわれています。
台湾の総人口は2020年時点でおよそ2,356万人ですので、人口の約14%が素食を選択していることになります。
ちなみに、台湾の卡優新聞網というメディアの情報によると、全人口に占める素食人口の割合としては、台湾はインドに次ぐ世界第2位の規模になるようです。
(出典:卡優新聞網「台灣素食人口世界第2 小七4大策略拼綠金」)
また、過去には米CNNから「The best cities for vegans around the world(世界で最もヴィーガンに優しい都市)」の1つに台湾の首都台北が選ばれたこともあり、台湾の素食・ヴィーガン文化が台湾国内だけでなく、世界的にも広く認知されていることがうかがえます。
(出典:CNN「The best cities for vegans around the world」)
なぜ台湾素食を選択するのか?
View this post on Instagram
台湾素食を選択する理由については、大きく次の6つに分けられます。
1.宗教的理由
仏教、道教の信仰者で、宗教的な戒律を守るために素食となっているようです。
戒律を厳格に守る方で、365日生涯ずっと素食を選択する方もいれば、「宗教上の法要がある日だけ素食」といった形で素食を取り入れている方もいるようです。
2.動物愛護の理由
動物愛護の観点で素食になる方もいます。
比較的若い層で、欧米の動物愛護的な考え方に影響を受けて素食になるという方が多いようです。
3.食糧問題・環境問題の理由
食糧問題や、食料の平等な配分といった理由で素食となる方です。
また、肉の生産により二酸化炭素と大量のメタンが排出されるという、肉食が環境に与える悪影響を知り、素食になる方もいるようです。
4.有名人の影響
自分の好きな俳優やモデルが素食なので、自分も素食になるという方です。
入口は有名人の影響ですが、そこから素食について色々と勉強し、生涯素食となる方もいるようです。
5.健康上の理由
深刻な疾患がある場合や、肉食が体質に合わない場合だけでなく、摂取飲食のバランスの調整のために、「今日だけ素食」「週末だけ素食」といった形で食生活に素食を取り込む方もいるそうです。
6.目標達成のため
何かの目標に達成するまでの一時的な間、素食になるという方もいるようです。
(出典:一般社団法人日本素食振興協会「素食になった理由」)
宗教上の理由で、生涯に渡り素食生活を導入する非常に厳格な形から、目標達成のために一時的に素食生活を取り入れる願掛け的な形まで、台湾における素食は、実に広範囲にわたる様々な理由により選択されているようです。
台湾素食が広く浸透してきた背景は?
View this post on Instagram
台湾素食の文化形成は、国内外の影響を受けながら、段階的に徐々に浸透してきたといわれております。
1980年代以前は、一般の人々の印象としては、素食主義者といえば、仏教や道教といった宗教と結びついている方々のことでした。
その後、1980年代以降では、欧米で生まれた新しいベジタリアン、すなわち健康と環境保護を訴える新しい菜食主義が、台湾の素食文化の更なる追加基盤となっていきました。 欧米でのベジタリアンの根拠は、環境保護、動物愛護、健康などの要素が多く、宗教的な要素はかえって主要因ではありませんでした。
近年では、台湾では環境保護運動や動物愛護運動が社会的に声高に叫ばれるようになり、環境保護や動物愛護の観点から奨励された素食運動が徐々に発展してきたと言われています。台湾の環境保護活動家の活動の影響等もあり、多くの人が自発的に素食運動に参加するようになりました。 これらの結果もあり、台湾の素食人口は更に増加していくことになりました。
また、台湾政府の活動が素食文化を推進・支援していることも、素食浸透の背景にあります。例えば、台湾の県や市、学校の食堂では、素食運動を推進するために、週に1日を「ミートレスデー」として、さまざまな素食プログラムを推進しています。
加えて、著名人による発信も、素食のトレンドを更に後押ししているといわれています。台湾芸能界のスターである女優・徐熙媛(Barbie Hsu)は、素食主義者であることを頻繁に提唱しており、多くの台湾人に影響を与えています。
View this post on Instagram
(出典:中国和平统一促进会「台湾的素食文化」)
まとめ
View this post on Instagram
いかがでしたでしょうか?
今回は「台湾素食」についてご紹介しましたが、台湾での素食(ヴィーガン・ベジタリアン)文化が段階的に形成されてきた背景は、非常に興味深いですよね。
台湾という国にとって「台湾素食」は、一時的なトレンドのようなものではなく、様々な歴史的・文化的背景により段階的に形成されてきた文化だからこそ、広く深く、浸透しているのかもしれないですね。