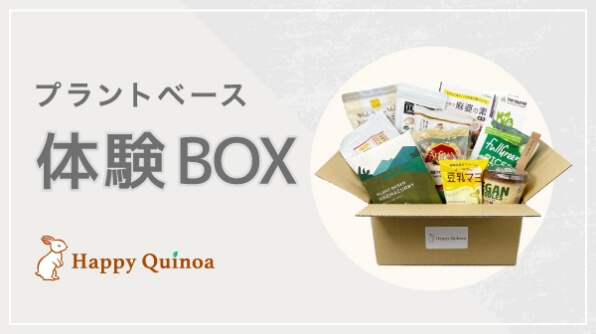外食時に摂りすぎてしまう栄養素とは?【ヴィーガンでもできる選び方の工夫】

外食時に摂りすぎてしまう栄養素と、不足してしまう栄養素とは?ヴィーガンの方におすすめする、外食時での食事の工夫について、管理栄養士が解説します。

そのため、ヴィーガン食では動物性食材を摂らず、植物性食材のみを食べます。
自宅での調理の場合、自分で使用する食材や栄養バランスを考えた調理ができますが、外食となるとそうはいきません。
とはいえ、家で料理を作る時間がないので外食や中食(コンビニやウーバーイーツなど)に頼っているヴィーガン・ベジタリアンの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、外食時での栄養面の工夫について、管理栄養士が解説していきます。
外食で気をつけるべき栄養素
塩分と脂質

ヴィーガン・ノンヴィーガンに関係なく、外食時に多くとってしまいがちな栄養素は、塩分と脂質です。
その理由として、塩分、脂質はどちらとも味の「満足感」に関係している栄養素であるため。
外食では「満足感」を感じることが大事なため、必然的にこれら二つの栄養素が増える傾向にあります。
特にファストフードやレトルトでは、塩分と脂質が多くなりがちになります。
精製された炭水化物

白米や薄力粉で作られたパンや白砂糖と、塩分、脂質の組み合わせは血糖値を急上昇させる原因となります。
血糖値の急上昇・急低下は、強い睡眠欲や空腹、低血糖、そして体重増加の原因となるためできれば避けるのが好ましいです。
加えて、精製された穀類にはビタミン・ミネラルがほとんど含まれないため、副菜などの工夫で補う必要があります。
たんぱく質

ヴィーガンやベジタリアンの場合、お店によってはメインディッシュでヴィーガン対応のものがないことがあります。
その場合、サイドメニューや主食となるご飯類のみの食事になってしまい、たんぱく質が不足しやすくなります。
1日のうち一食のみたんぱく質の量が少ない、程度であればそこまで問題ではありません。
しかし、体のあらゆる部分を作るたんぱく質を毎日継続的に摂ることは必要不可欠であるため、できれば毎食一定量摂ることが好ましいです。