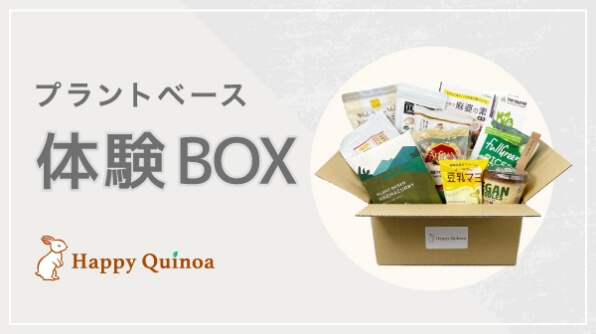エシカルとは?エシカル消費の正しい理解と、実践する具体的なポイント5選

世界中で幅広く取り組まれているエシカル。その基本的な概念から、日常生活でエシカル消費を実践するポイントを5つをご紹介します。ヴィーガン以外の方も必見な情報を多く掲載しています。

近年では、世界中で環境問題が幅広く取り上げられており、そのあたりのニュース記事で、見かけたことがある方もいるかもしれません。
しかし、その詳しい意味を知っているという人は、そこまで少ないのではないでしょうか。
そんな、近頃耳にすることの多い「エシカル(消費)」について紹介します。
エシカル消費の基本的理念

エシカル(ethical)とは、日本語では「倫理的な」という意味を持つ言葉です。
倫理的であるとは、社会的なマナーが守られている状態のことです。
つまりエシカル消費というのは、社会的なマナーを守る消費の方法であるということになります。
また、エシカル消費は、環境問題への対応から重要だとされる、持続可能な開発(SDGs)を実現するためにも非常に大切な概念です。
より具体的に説明すると、エシカル消費とは、下記3点が抑えられている消費のことです。
- 人にやさしい消費
- 地域にやさしい消費
- 環境にやさしい消費
それぞれについて少し説明すると、
はじめに、1つ目の「人にやさしい消費」とは、助けが必要な方へお金が回るような消費、あるいは、反社会的勢力にお金が渡ってしまうような消費を避けることです。
2つ目の「地域にやさしい消費」とは、地域社会・経済を活性化させる消費、あるいは、地域社会・経済を損なわないための消費です。
最後に、3つ目の「環境にやさしい消費」とは、これが最もわかりやすいかもしれませんが、地球環境を良くする消費、あるいは、地球環境を悪化させない消費をすることです。
(出典:エシカルとは?エシカル消費の押さえておきたい4つのポイント!|サステナブルジャーニー|大和ハウスグループ)
それでは本題の、エシカル消費を実践するうえで考えるべきポイントを紹介します。
エシカル消費を実践するポイント
1.「誰が」を考える

まず、誰がつくった製品なのかを考えてみましょう。
考える規模感としては、「港区の田中さんが」ということではなく、「アフリカの子供たちが」という感じです。
現在は、改善しつつもある国も多く、一口にアフリカだけを取り上げるのも良くないですが、アフリカの中ではまだまだ労働を強制されている子供たちが多いのが事実です。
こうした発展途上国の子供たちの製品は、品質はよいにも関わらず、かなり安価に先進国と取引されてしまうことが多いのです。
売れれば売れるほど、より多く生産しなければならなくなり、労働時間が長くなってしまいます。
収入が得られそうで良いのでは?と思う方がいるかもしれませんが、実際には働いている方へ渡るお金は非常に少なく、中には一切もらえないという状況があります。
こうした状況を排除し、適切な品質の製品を、適切な量、適切な価格で取引するフェアトレードという仕組みがあります。
フェアトレード製品を購入・消費することで、生産者の方の安定した生活をサポートすることができます。
これにより、生産者の人権を守る倫理的行動、すなわちエシカルなアクションをすることができます。

同様にハンディキャップを持った方の自立支援のため、そうした方々が生産した製品を積極的に消費するのもエシカルな行動です。
また、消費者だけではなく、経営者の方も、ハンディキャップを持った方を積極的に採用し、労働の機会を適切に与えることが大切です。

野菜や果物のパッケージなどでも目にすることも多い「〇〇さんがつくりました」という表記。
これは、消費者の安心を第一に考えたものですが、消費者が購入者に対して感謝の気持ちを持つことができる、一種のエシカルな体験ですね。
消費者の立場でも、生産者・経営者の立場でも、自分の行動が誰のためになっているのかを、よく考えることで、エシカル消費をすることができます。
2.「どこで」を考える

消費しようとするものが、どこで作られたものなのかを考えることも、エシカル消費には重要です。
「どこで」を考えるにあたって重要な概念は、皆さんも一度は耳にしたことがある「地産地消」です。この地産地消とは、地元で生産されたものを地元で消費するということです。
そのメリットをいくつかご紹介します。
まず、地元で生産されたものを地元で消費することで、輸送コストを抑えることができ、二酸化炭素排出量を削減することができます。遠く離れた場所から運ばれたものは、それだけ輸送コストがかかります。
そのため、自動車・船・飛行機などで運ばれてくれば、多くの二酸化炭素を排出してしまいます。
地元で消費できれば、基本的に船や飛行機で運ぶ必要はなくなるので、その分の二酸化炭素排出量を削減することができるのです。

また、地産地消の活動を通じて、生産者と消費者の心理的な距離を近づけることができます。
そこで深い繋がりができれば、地域にやさしい消費を実践できるだけでなく、食料自給率を高め、結果的に地球環境の保護にもつながります。
人・環境・地域に優しい地産地消することで、エシカル消費を実践することができます。